世界のマエストロ、小澤征爾さんが、この2月に亡くなられた。その輝かしい業績を振り返ってみるたびに、あまりにも充実した音楽人生を全うされたことを思い知らされる。僕は小澤さんの演奏をフォローし続けてきたわけではないのだが、一音楽ファンとして、小澤さんの名盤と呼ばれたアルバムは多く耳にして、大きな感動も受けてきた。そんなアルバムの中からオーディオ的にも忘れられないものを選んで、偉大だったマエストロを偲んだ。
♯244 パリ管弦楽団を振った2枚の名盤をカップリング
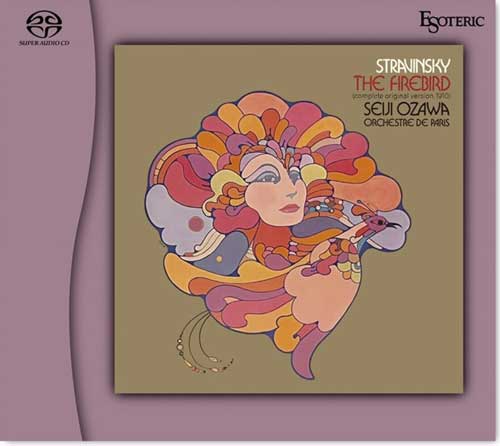
「チャイコフスキー:交響曲第4番、ストラヴィンスキー:火の鳥/小澤征爾指揮 パリ管弦楽団」
(Esoteric ESSW-90281~82)
よく言われるように、小澤征爾が大きく注目されるようになったきっかけは1959年にブザンソン国際指揮者コンクールで優勝したことだったが、この時の審査委員長だったのがシャルル・ミュンシュ。そのミュンシュを音楽監督に迎えて67年に創設されたパリ管弦楽団に、小澤は70年代に何度も客演した。そんなパリ管弦楽団を指揮して70年と72年にEMIに録音された2枚の名盤がカップリングされて、エソテリックからSACDハイブリッド仕様で昨年(2023年)秋に復刻リリースされた。まだ30代半ばだった若きマエストロと、設立されて間もなかったオーケストラによる熱い演奏。日の出の勢いで国際的な名声を得ていった小澤が、ほんとうの意味で“世界のオザワ”になっていった頃の溌溂たる響き。
チャイコフスキーの「交響曲第4番」は、作曲者が37才のときの作品。慟哭ともいえるほどの激しい感情の起伏をもっているものの、その底流にはチャイコフスキーならではの、ほの暗い抒情が一貫してながれている。それは抒情というよりも重く、悲劇的でさえあるが、メロディーの流れはあくまで自然で暗く、美しい。もう一枚はストラヴィンスキーのバレエ音楽「火の鳥」。よくある“組曲”でなく“全曲版”で、長さは組曲版が20分程だったのに対して46分あって、編成も大きい。有名な<春の祭典>の3年前になる1910年、作曲者が27才の頃の作品で、事実上のストラヴィンスキーの出世作になったもの。色彩感あふれるオーケストレイションとともに、それぞれの曲の細やかな楽器の動きの意味合いや精緻なハーモニーを際立った美しさで導き出してゆく小澤の統率ぶりが、じつに見事。新たにマスタリングされたハイブリッド盤では、そんなオーケストレイションの素晴らしさが一段と引き出されているように思う。
♯245 “花の章”を加えたマーラーの第1番
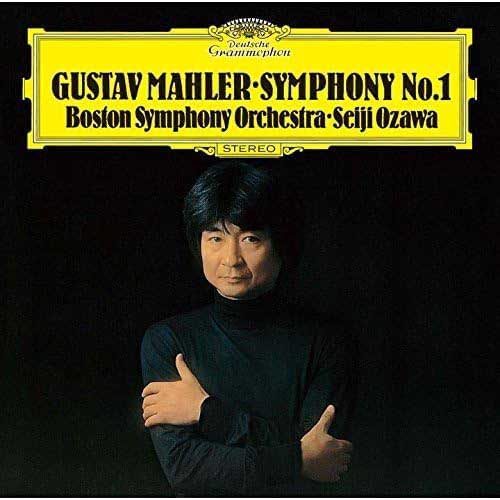
「マーラー:交響曲第1番“巨人”/小澤征爾指揮 ボストン交響楽団」
(ユニバーサルミュージック UCGG-9514)SACD
1973年にウィリアム・スタインバーグのあとを受けてボストン交響楽団の常任指揮者、音楽監督に就いた小澤征爾。以来、およそ30年にも及ぶ蜜月の中で、たくさんの名演が残されたアルバムの中から、グスタフ・マーラーによって1884年から88年にかけて書かれた「交響曲第1番」を、あらためて聴く。このあとも小澤は同曲を何度か再録音しているけれども、この77年の演奏は一回目のもの。普通には4楽章で演奏されるが、もともとは“花の章”が加えられて5楽章の構成をとっていた。
初演時にはあったものの、すぐに作曲者自身の手で取り除かれた“花の章”。そんな楽章をあえて加えて演奏しているのも興味深い。複雑さ、壮大さをもついっぽうで、子供のように無邪気な表情もみせるマーラーの音楽。まだ20才代半ばだった頃のマーラーのこの作品では、青春時代の苦悩や夢が描かれる。全体にテンポをゆっくりとって、確かな表情で大らかに描かれるマーラーの世界。77年の録音でアナログ時代の名盤であるが、本SACDシングルレイヤー盤は2012年にドイツのエミール・ベルリナー・スタジオで8チャンネルのオリジナル・アナログ・マスターからリミックスされたDSDマスターを使っていて、音質的にも複雑なマーラーの音楽の細かなディティールまでを、くっきりと浮かび上がらせている。
♯246 武満徹の代表作、不朽の名演

「武満徹:ノヴェンバー・ステップス 他/小澤征爾指揮 サイトウキネン・オーケストラ」
(ユニバーサルミュージック UCCD-45003)
小澤征爾のレパートリーは、とても幅広い。古典派から得意のフランスもの、近代の作品まで、スコアの隅々までを読み通したうえで、どれもが情熱的で雄弁な語り口で迫ってくる。そんな多彩なレパートリーの中でも、ひときわ印象に残っているのが武満徹の作品集。1967年、ニューヨーク・フィルハーモニックの創立125周年コンサートのために書かれた<ノヴェンバー・ステップス>は、和楽器の尺八と琵琶を西洋のオーケストラと対峙させるという斬新な試みがなされている。リンカーン・センターのフィルハーモニック(現デイヴィッド・ゲフィン)・ホールで初演をおこなったのが小澤征爾指揮のニューヨーク・フィルで、尺八は武満作品に欠かせない横山勝也、琵琶が鶴田錦史。以来この曲は武満の代表作として、多くのオーケストラによって演奏されてきた。これは89年の録音で、もちろん尺八と琵琶を横山、鶴田が演奏している。
サイトウキネン・オーケストラは84年、小澤の師でもあった齋藤秀雄の10周忌を期に編成されたオーケストラで、世界的にも大きな評価を得ている。不協和音が連なる抽象的な響きをもった作品を、誰もが納得してしまうような楽想のうねりで聴かせてゆくのが凄い。後半に展開されるふたつの和楽器だけのカデンツァの部分で、息詰まる緊張感が保ち続けられてゆくのは、小澤ならではの神業だ。尺八の生々しい息遣い。琵琶の鋭い撥使い、オーケストラのクラスターをリアルに体験するのは、オーディオの醍醐味でもある。円熟を増していった武満が89年に書いた、ヴィオラとオーケストラのための<ア・ストリング・アラウンド・オータム>なども併録している。
筆者紹介

岡崎 正通
小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。

